|

●2023年4月号
■ 春闘の行方を追う
平地 一郎
現在、春闘の真っ最中だろう。なのにその「行方」などと、のんびりしたテーマで書くことになった。
今年の春闘は、特別の意味を持つかもしれない。春闘が抑え込まれて半世紀近くが経ったが、その環境条件や課題への対応などに変化が生じていると考えられるからである。そうした変化をみることを通して、春闘がいったいどこに向かうのかを考えたい。その1つの試みである。
■ 春闘の歴史
最初に春闘の歴史を振り返る。原資料等に当たる余裕がないので、ざっくりとした春闘史である。
春闘は1955年に始まった。
その前の1950年代前半は「産業別賃金決定の混乱」の時代と言われ、1949年の改正労働組合法(新労組法)を後ろ盾に、資本側は、経営内の労働組合の協議決定権と産業レベルでの労働協約の締結を否認したため、労働側は戦後初期の労働攻勢と打って変わって守勢に立たされていた。労働側の模索が続いた。
その模索の中から、事態を打開するべく考案されたのが、春闘という方式である。
政党あるいは組織が機関決定して春闘を始めたわけではない。強いて言えば、雑誌『社会主義』の同人を中心に労働者同志会につどった人々が、創意工夫の末に編み出したものであった。春闘は、企業別組合という現実を踏まえて、賃金引き上げを産業別統一闘争によって達成しようとした。その提唱者である太田薫の言葉どおり「暗い夜道もお手々つないで行けば怖くない」というものだった。
もとより、彼らの志は高かった。そうした恐る恐るの春闘ではあるが、それを支える労働組合の強化も目指された。1958年には、総評大会で「組織綱領草案」が討議されたが、これは労働組合の基礎に職場闘争を置こうという提起であった。総評組織綱領草案は、当時の炭労三池労組や私鉄総連北陸鉄道の実践を踏まえたものであり、職場闘争を基礎にして産業別労働組合への道が展望された。実践的には「企業別組合の強化を通して企業別組合からの脱皮を図る」(三池労組の灰原茂雄)ということになるだろう。
なるほど、総評組織綱領草案は、1960年代前半に「棚上げ」され、総評の公式の方針にはならなかった。しかし産別の中では真剣に討議・検討され、その後、私鉄総連・国労・自治労・日教組・全逓などでは、組織綱領草案は内容としては生きて行くことになる。今日、これらの産別の多くが労働組合として光を放つのは、総評組織綱領草案を抜きには考えられない。
わずか8単産70万人で始まった春闘は、10年後の1966年には、700万人をこえた。しかも総評外の労働組合を含めれば850万人の賃金闘争が闘われるようになった。じつに、全組織労働者1100万人の8割にあたる。そして春闘の結果は、3000万人におよぶ雇用労働者の賃金に直接、間接に大きな影響力をもった。規模別賃金格差も着実に縮まっていった。
右の数字は、春闘共闘委『賃金白書』からとったこともあり、少し誇張がある。労働省の調査より100万人ほど多い。ただ、そう大差はないし、むしろ少しの誇張は、自信の表れでもある。春闘は、もはや「夜道」などではなく、働く者の声援を受けながら、白昼堂々と歩いていた。
そして国民春闘を掲げた1974年春闘は、その前年秋のオイルショックによる狂乱物価の中で闘われ、賃上げ率32.9%を獲得するにいたった。
春闘の闘い方をめぐっては、もちろんさまざまな論争があった。その1つに、1960年代初めの横断賃率論争がある。研究者内での論争は別にして、総評内でも真剣に議論された。横断賃率論とは、企業を横断して産業別に賃率を設定し、春闘を闘おうという主張である。それに対して、私の印象では、戦後の労働運動を一から立ち上げた労使対抗的な左派の人々は、総評賃金綱領のマーケット・バスケット方式にこだわり、賃金配分に不満であった青年層も、大幅賃上げで納得すると考えた。
この論争は大幅賃上げの中で、うやむやに終わった。果たしてどちらの主張が正しかったのか。この場合には、両方とも正しかった。
本来は、対立する論争ではなかったからである。1947年労働基準法第四条(男女の同一労働同一賃金)以来、理論的にはすでに決着していた問題である。東大社研の氏原正治郎が整理して書いていたように、賃金が労働力の価格なのは、資本家と労働者との関係においてであり、同一労働同一賃金が重要なのは、労働者間の配分問題としてである。したがって、横断賃率論に反対した当時の総評調査部長・小島健司も、横断賃率の前提として「わが国の初任給が現在の3倍ないし4倍くらい引き上げられること」と「失業保険の拡充を中心とした社会保障と最低賃金制の確立」をあげた。
1970年代には、右の2つの条件は、ほぼそろっていた。ところが、その時には、横断賃率論を掲げた人々はさほどこだわらなくなっていた。会社あっての労働者である。会社を守り、雇用と社員としての身分を守る。会社都合の配置転換であっても賃金が変わらなければ率先して応じる――1970年代前半までの春闘と労働運動の高揚を前にして、資本は、労使関係の安定には、職場こそが要諦であると見ていた。民間大手では、年功的処遇によって、職場での不満を一つ一つ摘み取りながら、労働組合の影響を排除していった。これが「企業中心社会」現象の背景である。企業を横断する賃金という発想は出て来ようがなかったのである。
このように外堀を埋めた上で、1980年代、資本は総評の牙城である国労攻撃に乗り出した。新聞・マスコミそして世論なるものも総動員して、国労を叩き、分割民営を推し進めた。国家的不当労働行為が、白昼堂々とまかり通った。国鉄内で功があった者たちは、その後JR各社の社長に栄進した。経営手腕とは、不当労働行為の才能だったのか。彼らには、踏まれた者の痛みは分かるまい。
総評が解散し、連合が発足した。その1990年代以降は「失われた30年」である。「歪められた30年」と言い換えてもよい。
連合が、そうした歪められた30年に責任があるとは言わないが、その歪みを是正する力には欠けた。春闘も総じて低迷した。
とはいえ21世紀に入って、いくつか注目すべき事柄が起きた。その1つは、連合評価委員会報告である(2003年)。社会的労働運動と同一価値労働同一賃金による雇用形態を超えた連帯の呼びかけは、真剣に受け止められるべきものであった。2つは、連合会長選挙で全国ユニオン(組合員3000名)の鴨桃代会長が代議員の4分の1近い票を得たことである(2005年)。労働運動の底流に流れるものを実感させた。今後の春闘(労働運動)の行方を考える上で、いずれも重要な出来事だった。
空前の大幅賃上げを勝ち取った74年国民春闘から、半世紀が経とうとしている。そしてつぎに見るように、春闘の環境条件に変化が起きていると思われる。丁寧に分析したい。
■ 春闘の環境条件
春闘(労働運動)の環境条件に変化が見られると私は考える。二点をあげたい。
1つは、やや長期的な傾向で、女性の雇用化が進む中で、従来の家族観に劇的な変化が見られることである。選択的夫婦別姓やLGBTQなどに関しては、若い世代ほど理解が深く、それゆえ支持も大きい。そうした価値観の転換の時期は、従来の支配的な枠組みは揺らぐものである。“情勢は昨年と同じ”というやり方は通用しない。後述する。
2つは、より直接的な契機で、現在のインフレの進行である。そして昨年あたりから、人々(労働者)の行動変容が見られる。自己責任や節約生活での対処に限界があって、賃金を上げるという選択肢が現実味を帯び始めている。
そのインフレと賃金という後者のテーマから見ることにしたい。
・1. インフレと行動変容
2023年の春闘において、連合は「デフレマインドを断ち切り、ステージを変えよう」との主張である(春季生活闘争基本構想など)。現在の経済状況と労働者の思いをかなり適確に踏まえたものだと思う。というのは、労働者の意識と行動において、デフレマインドからの離反が現実に進んでいると考えられるからである。
その状況を見るには、渡辺努『世界インフレの謎』(講談社現代新書、2022年10月)が参考になる。
同書によれば、
- 現下のインフレの原因として、コロナ禍を契機に世界的には人々(消費者・労働者・企業)の行動の変化が見られる(サービス消費からモノの消費へ、労働供給の減少へ、グローバル化から国内化へ)。この行動変容が新たな価格体系に反映されるまでインフレは続く。
- 日本の場合は、デフレ下にあって(慢性デフレ)、賃金も商品価格も据え置くという労使双方のノルム(規範)が効いて、賃金は上がらなかった。しかし、世界的なインフレからの影響(急性インフレ)によって、そうしたマインドに変化が生じている。
右の「2.」が進めば賃金上昇と商品価格への転嫁という「好循環」が生まれるというのが、同書での1つの予想である。インフレの原因および将来の予想は、さしあたり置くとして、重要なのは、そうした主張の根拠として挙げられているつぎの事実である。
渡辺研究室が毎年実施しているアンケート調査では、諸外国と違って日本では、2021年まで大半が物価は上がらないと予想していたが、2022年8月のアンケート結果は、上がると予想する人の割合が欧米並みになった。そして、商品の購買行動が大きく変わった。従来は、商品が値上がりしている場合、安いものがあるはずだと他の店に足を運んでいたが、今ではその商品を買い続けるようになったのである。
このような同書が明らかにした事実を踏まえると、2021年には商品の質と量を下げて価格を据え置く「ステルスインフレ」だったものが、2022年からは「価格転嫁」へと傾き始めている企業行動もよく理解することができる。消費者(労働者)も企業も、デフレマインドから「脱却」し始めているのである。
賃金もまた、労働力という商品の価格である。この場合、デフレマインドからの脱却とは、物価が上がっているのだから、賃上げは普通のことだという売り手側(労働者)の自然な意識と行動を意味する。春闘の議論と準備が始まった昨年秋以降、おそらく連合の当初の予想を超えて産別・単組の賃金要求の声は強まっているだろう。
こうしたデフレマインドからの労使の離反をもっとも敏感に表しているのは、JAMの提起する価格転嫁の要求である。言うまでもなく、JAMは、機械・金属製造業の主として中小企業における労働組合の産別組織である。中小企業の大手独占への納入商品は不当にも低い価格に抑えられてきた。原材料等の上昇分を価格転嫁し、賃上げも同時に行う闘いである。2016春闘から公正取引問題として取り組まれている。
賃金要求とは労働契約の変更要求を意味する。その要求・闘いがなければ、労働契約の上で労使対等である事実は、大衆的・経験的に意識されにくい。労働運動にとっても、デフレマインドからの脱却が持つ意味は大きい。賃金要求と労働運動の「好循環」である。
・2. ジェンダーギャップと労働組合
女性の雇用化と家族観の変容については、これだけで一書を要するほどの問題である。かいつまんで言えば、女性が労働者として働くということは、従来の家族観にある性別役割分業規範―男は仕事、女は家事・育児―との矛盾を深める。男女が等しく労働し生活していくためには、そうした家父長制的家族観とその制度は足かせになる。それが、家族観における変容・あるいは揺らぎの背景である。
そうした変容の象徴として、選択的夫婦別姓問題がある(その説明は不要であろう)。メディア等の世論調査は、その支持が多数を占めることを示しているが、内閣府世論調査でも同様である。法改正が議論された1996年から約5年ごとに実施されてきた調査では、2018年には、「夫婦は必ず同じ名字を名乗るべきだ」とする回答29.3%に対し、「選択的夫婦別姓制度の導入に向けた法改正について賛成」は42.5%を占めた。年代別に見ると、反対が圧倒的に多い70歳以上を除けば、どの年代も賛成が多く、18歳〜39歳層では過半数そして40歳〜59歳もほぼ半数という割合である。その他、階層別に見ると、自営業層と専業主婦世帯で反対が多く、共働きの勤労者世帯では圧倒的に賛成になる(2022年の調査もあるが、質問事項が恣意的に変更されたと見られ、比較できない)。
夫婦別姓(夫婦別氏)に関する世論調査は以前から行われていて、1987年には、賛成が13.0%、反対が66.2%であった(法務省)。単純な比較はできないが、この30年間で夫婦別姓に関する人々の意識はずいぶんと変わったと見てよい。すなわち、家族観の変容とでも言うべき事態である。
性別役割分業がジェンダー不平等の主要な原因である。2006年に世界経済フォーラムが、ジェンダーギャップ指数(GGI:Gender Gap Index)の公表を開始してから、ずっと日本は低位にある。しかも他の先進諸国が改善するなかで、日本はそれすら見られない。2022年のGGIは、0.650(146カ国中116位)である。4分野(経済・教育・健康・政治)のうち、経済と政治の分野でのギャップが大きい。
その改善のカギは労働組合にある。ここで試しにOECD諸国(38カ国)における組合組織率とGGIとの相関係数を計算すると、強い相関を示す0.60という値である(視覚化するとグラフ参照)。統計データの分析からは因果関係は分からないが、経験的には労働組合の存在とその運動がジェンダーギャップを小さくすると十分に推測できる。職場に労働組合の影響があるかどうかで違うだろう。
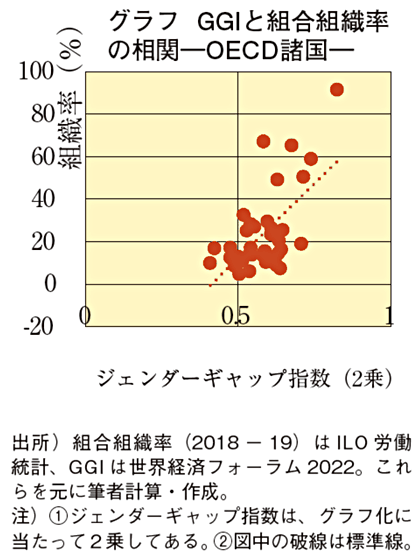
(図1・クリックで拡大します)
また、労働組合の要求が社会的かどうかでも違う。たとえば現在の育児休業制度のみなもとの1つは、1960年代の全電通(当時)による育児休暇制度の要求にある。休暇が休業に変更されて妥結しなければならなかったという苦い経験はあるものの、一応そうして始まった。とはいえ、休暇の対象を女性とすれば性別役割分業規範を強める。また男女双方だとすれば、妻と夫が同じ企業で働いているとは限らない。つまり企業内では限界がある。社会的制度化へと発展する要求である。
1970年代以降優勢となる企業中心社会は、性別役割分業と年功的労使関係とが補強し合う構造で成り立っていた。育児・教育・障害・失業・介護など、本来は企業を横断する社会的課題に対する視点は後景に退いた。しかし今日では、女性の雇用化によって職場と家庭との関係は大きく変化している。
春闘が始まって、最初の20年の前進期そして後半の半世紀に及ぶ後退期・低迷期を経て、その環境条件は変化しつつある。まずは産別の賃金要求の条件が整い、そしてその要求の社会的課題を企業・産別を超えて統一要求に押し上げる。そういう春闘の再出発(春闘の行方)でありたい。
(2023年3月19日 ひらち・いちろう)
|