|

●2022年12月号
■ 第210回臨時国会の終盤に向けて
――暮らしと命、平和を守る闘いを強めよう――
小笠原 福司
■1. 上場企業― 4〜9月―2年連続最高益―
前述の中見出しは、日経新聞(以下、日経と略す)の11月16日の見出しである。東証プライム市場に上場する3月期企業で11月14日までに決算を発表した1159社を日経が集計した。増収率も20%と金融危機後で最高で、全36業種中21業種、約6割が増益となった。
けん引したのは非製造業。純利益は8%増の10兆7372億円と、増益率・利益額ともに製造業を上回った。
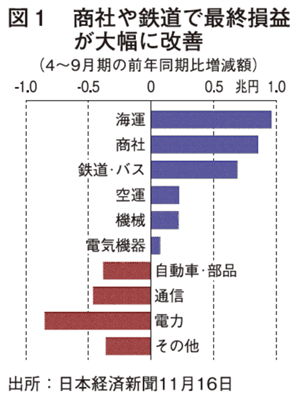
(図1・クリックで拡大します)
図1で見るように、利益を大きく伸ばしたのは、海運や商社。そして、経済再開で鉄道や空運の復調。他方で、苦戦したのは電力で大手9社が最終赤字に転落。資源高に円安が加わり燃料調達コストが急増したことによる。
製造業は円安が利益を支え1%増益。4割が「増収減益」型である。半導体不足や原材料高で自動車・部品が減益。電機も低調となった。なお、主要約100社の円安による増益効果は3兆円超となり、8割強が製造業であった。
そして、円安を受け2023年3月期の業績見通しを上方修正する企業が全体の31%に上った(上方修正額は2兆9000億円)。純利益を集計すると前期比7%増の見込みで、8月中旬時点より増益幅が拡大した。
一方で内閣府が15日発表した7〜9月期の国内総生産(GDP)は4四半期ぶりに年率換算で1.2%の減少となった。マイナスの最大の要因はGDPの半分以上を占める個人消費の低迷である(実額は298兆円と、コロナ危機が深刻化する直前の20年1〜3月期の296兆円とほぼ同水準で、19年10月の消費税増税前の300兆円台を下回ったまま。この間の実質賃金は1.7%減―厚労省毎勤統計)。生活必需品の値上げが相次ぎ節約志向が広まる中、国内消費の状況は予想以上に深刻で上向く気配はない(なお、GDI=所得面から経済規模を示す実質国内総所得で、暮らし向きを把握する、は年率換算で前期比3.9%減とGDP以上に悪化した)。
上場企業の4〜9月期決算については、前述したが、この間の円安傾向を背景に民間非金融法人のため込んだ現預金残高は、22年3月末で323兆円と昨年12月末から8兆円の増加で過去最高を更新している(「ニッセイ基礎研究所」、「資金循環統計」22年1〜3月期)。消費を回復させ低成長から「持続可能な経済成長」軌道に乗せるには、大企業を中心として厖大にため込まれた現預金を労働者に「公正・公平に分配」(大幅な賃上げ)することである。特に、日本経済を支えている中小企業労働者の賃金引き上げが喫緊の課題として問われている(大企業との公正取引の実現に向けての課題は、本誌黒瀬直宏氏論文を参照)。
■2. 生活破壊と政治反動をすすめる岸田内閣
岸田政権の無策が続く中、総務省が18日に発表した10月の全国消費者物価指数(2020年=100)は、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が103.4と、前年同月比3.6%上昇した。食料品など生活必需品の値上げラッシュやエネルギー価格の高騰が響き、第二次石油危機の1982年2月以来、40年8カ月ぶりの高い上昇率を記録した(日銀が9月に調査した「生活意識に関するアンケート」では、1年前に比べ現在の物価上昇率は10%=中央値と言う結果)。
しかし、その内実は「当時は3.6%のうちエネルギーと食料が占める割合は約4割だったのに対して、今年10月は7割以上を占めた。生活実感としての値上げの影響は40年まえよりも大きいといえる」(ニッセイ基礎研究所の斎藤太郎経済調査部長)と分析されている。
みずほリサーチ&テクノロジーズの酒井才介氏の試算では、政府の物価高対策を考慮しても2人以上世帯の負担額は22年度に平均9万6000円、23年度はさらに4万円上乗せになるという。年収の低い世帯ほど生活に欠かせない食料品値上げの影響は大きいことは言うまでもない(第二次補正予算で標準世帯のエネルギー関連支出が来年1月から9月の9カ月間で総額4万5000円ほど少なくなるとのことだが、前述した負担増の3分の1程度)。多くの企業が通期決算をしめる年度末に向けて食品の値上げ、再値上げに踏み切る動きが強まっていて、来年に2月以降、値上げラッシュが再び大きな山場を迎える可能性が高いと予測されている。
物価高や円安による収益悪化が原因で倒産する企業が増えている。帝国データバンクは9日、「物価高倒産」が10月に41件と、4カ月続けて過去最多を更新したと発表した(運輸業や飲食料品小売業が目立つ)。「円安倒産」も7件と、8月に並んで今年最多(このまま推移すれば過去5年間で最多の可能性)。中小・零細企業は仕入れ価格の上昇分を販売価格に転嫁しづらく、今後しばらく増加基調で推移すると指摘されている。
一方、東京商工リサーチが集計した10月の企業倒産件数は(負債1000万円以上)前年同月比71件(13.5%)増の596件となった(理由に新型コロナウイルス禍が含まれるものは43%増の230件で、2カ月連続で最多を更新)。今年4月以降、7カ月連続で前年水準超えが続いている。また、同調査では「過剰債務が事業再構築の足かせになっている」中小企業が35%になっている。年末に向けて債務の一定範囲の減免、新たな資金調達施策などが問われている。
岸田文雄政権は「総合経済対策」で「構造的な賃上げ」を掲げているが、中小企業を直接支援する施策はない。22年度第二次補正予算に盛り込んだのは業態転換や生産性向上への補助制度で、コロナ危機で苦しむ中小企業に直接届く支援ではない。
物価高対策に向けて岸田政権は第二次補正予算を組む。今月21日からその審議が国会で始まった。実は当初は25.1兆円であったが一夜にしてプラス4兆円の29.1兆円となった(8割は国債増発で賄う)。その背景として「支持率が下がり続けているのをリカバーするため」とのこと。自分の財布であるかのように、一夜にして4兆円も増額など、「とても先進国の予算編成とは思えない」との指摘は至極最もである。さらに、財政赤字が深刻になり国民への「大型増税」が取りざたされている今日、消費税10%で年間21.9兆円の税収だが、それを上回る補正予算(赤字国債発行による放漫財政)を組むことの正当性も疑われる。
「コロナ予備費の12兆円、9割が使い道が判明していない」、「どう思いますか」(日経電子版、4月22日)とは、日経新聞が自社の広告として載せた問いである。ご承知のように予備費は国会審議を経ず、閣議だけで決めて自由に使え、これが政権基盤の維持、強化に使われてきたことは言うまでもない(22年度の予備費の総額は約11.7兆円)。財政民主主義の観点からも、岸田政権は安倍、菅政権と同様に「民主主義」を公然と破壊しつつ、政権維持を図っている。
「民主主義の破壊」の最たるものとして岸田首相は、安倍元首相すら踏み込めなかった原発再稼働、運転期間の延長、さらに新型炉の建設までやると決めた。それも参院選前には決めていたがひた隠し、選挙後の7月27日に指示を出している。「安全・安心」、そして命に関わる事態であり、「丁寧に話を聞く」など眉唾ものである。
最後に、本年末とされる「安保関連3文書」(新たな国家安全保障戦略、防衛大綱、中期防衛力整備計画)の改訂である。9月22日、「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議」が発足した。同会議は、防衛力の抜本的強化に向け、自衛隊の装備のあり方や予算規模、財源などを議論することを目的として、「安保関連3文書」の改訂や予算編成に向け、12月上旬に提言をまとめることになっている。
すでに、日本の防衛政策の大転換となる「専守防衛」を踏み破る「敵基地攻撃能力」の保有が検討されている。看過できないのは政府が米国製巡航ミサイル「トマホーク」(日本海に展開するイージス艦から北朝鮮や北京に届くため、反撃能力として使うことが想定されていて、「憲法九条の下では保有することが出来ない」としていた長距離爆撃機よりも攻撃的)の購入を早くも米政府に打診していることが、既成事実のように報じられていることだ。さらに2030年を目途に「極超音速ミサイル」配備も念頭とのこと。政府側も「検討中」と国会での議論もないまま、臨時国会を閉じた後の「安保関連3文書」改定で決めてしまうのか。国会・国民愚弄も甚だしい。本来なら解散・総選挙で国民に問う必要がある。防衛予算増強(22年度の5.4兆円から27年度に10兆円超を目指し、5年間で48兆円)に反対し国民的議論を巻き起こし、何としても阻止しなければならない。
■3. 野党の院内外の闘いの強化に向けて
参院選に「勝利」した岸田政権に対して、「黄金の3年間」などとマスコミでもてはやされていた。しかし、安倍元首相の国葬を国会にも諮らずに閣議決定で決め強行した。世論は国葬前、後とも6割前後が「反対」の意思を示した。そして内閣支持率が40%前半から30%後半(政権寄りとされる読売新聞でも36%―11月7日)へと下がった(自民党支持も下がり、保守層からも見放されている状況)。
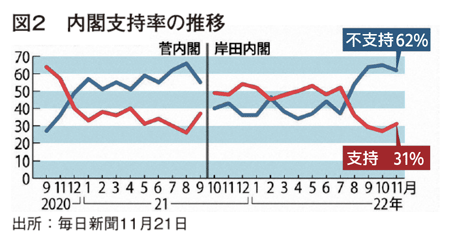
(図2・クリックで拡大します)
その不支持の層の根底には「物価高に対する無策」、世界平和統一家庭連合(以下、旧統一教会)と自民党との癒着解明への消極性などがあることは言うまでもない。そして、法律を無視し、丁寧な説明責任を果たさず国葬を決定したことに対して、学者、文化人など保守リベラル層も含めて「反対」のうねりが全国的に広がった(2014年の戦争法案廃止の闘いを想起させた)。無論、主体である立憲野党(立憲、共産党、社民党、れいわ)を中心とした粘り強い働きかけがあったことは言うまでもない。
改めて「安倍政治とは何であったのか」について想起させた。と同時に、「それを継承している岸田政権・政治とは何を目指しているのか」(世論調査の不支持の理由は、「政策に期待ができない」が最も多い)を国民に考えさせる時を与えたのではないか。そして、山際経済再生担当相、葉梨法務大臣、さらに寺田総務相の辞任と、この1カ月で3人の閣僚辞任=事実上の更迭となった。自民党内からも「もはや政権末期の様相で、第一次安倍政権の崩れ方だ」との声すら上がっている。
国葬の強行以降、世論の反対を背景にして国会内では野党第一党の立憲民主党(以下、立憲と略す)と日本維新の会(以下、維新と略す)の共闘が構築され、旧統一教会問題の被害者救済をめぐり共同で法律案を作成し、今国会での成立を目指した。こうした世論を背景とした国会内の野党共闘に押されて政府も新たな法案の概要を示した。野党側からは実効性に疑問の声が上がっていて、「骨抜きになる」懸念が出されている。今国会への提出と成立は不透明といえる。
今回立憲野党との共闘に消極的であった維新が、立憲と共闘を組んで自民党側に法案まで提出するに至った背景について様々な意見が飛び交っているが、根本には「まずは、一刻も早い被害者の救済をすべき」という世論の支持があることは言うまでもない。その一点で野党第一党と第二党が共闘を組んだということである。ここでも基本は被害者であり、徹底して国民の立場に立つ、という当たり前の政治であり、こうして政策ごとに共闘を積み上げていくことで立憲野党への国民の支持を広げることではないだろうか。「一強多弱」の国会内の野党としての闘い方である。
さて、臨時国会の終盤に向けて本格的に国民の暮らしと命、平和を守る闘いが始まる。本誌の飯山満氏の論文に政府の総合経済対策、そして立憲、維新、共産、社民、れいわの短期・中期の経済対策、経済構造転換の政策が分析されている。
問題は、「一強多弱」という国会勢力を踏まえて、あくまでも国民の暮らしと命、平和を守る一点での「共通政策」を早急につくる努力が求められている。その中心的柱は、40年8カ月ぶりの物価高に対する直接的な支援。中小・零細企業の倒産、廃業を防止する施策。農業、漁業への支援の強化。年金引上げ、医療・介護など公的負担値上げ中止。防衛費の増額に反対、など緊急を要する施策について、実施に向けた財源の確保含めて自公政権に対抗する「共通政策」(例えば23年3月末までの政策とする)を提示する取り組みである。
その土台は、昨年の第49回衆院選での「野党共通政策」、さらには今臨時国会に向けて、10月11日市民連合が立憲、共産党、社民党の三野党に12項目の政策課題の要請書を提出した。これらも含めて臨時国会の後半に向けて早急に最大公約数として「野党共通政策」作りが求められている。こうした積み上げを通してこそ国民からの信頼も得られる。それを国政選挙における野党共闘の深化につなげ、その先に野党の連立政権の展望を見出すことではないだろうか。そう考えると臨時国会における野党共通政策作りと闘いは、連立政権に向けての下稽古といえる。
■4.「先進国並みの賃金水準」を目指して闘おう
「先進国並みの賃金」(本誌特集の、JAM安河内賢弘会長の提起)という見出しをつけたが、読者の中には、かつて60年代の後半に「ヨーロッパ並みの賃金を」というスローガンを掲げて春闘を闘ってたきた経験をお持ちの方もいると思う。昨年の衆院選、今年の参院選で、「低成長から脱出し、持続可能な経済成長を如何に図るのか」という論争の中で、「先進国の中で、日本は20数年間賃金が上がっていないこと」が驚きをもって世の中の話題となった。
もう「日本は先進国どころか、成長しない国になった」「米国や英国は1995〜2021年で賃金が2倍超に上昇、韓国は3倍だ。各国とも物価も上がったが、賃金の伸びが上回る。日本はいずれも横ばいだった」(ニッセイ基礎研究所・上野剛志氏、図3を参照)
とのこと。芳野友子連合会長は、「歴史のターニングポイント」と、物価も賃金も上がる「普通の国を目指そう」と提起されている。本誌でも度々とりあげてきたが岸田首相の「新しい資本主義」などという眉唾物の政策が謳われているが、それは資本主義そのものが行き詰まり「存続しえない」という危機感のあらわれでもある。
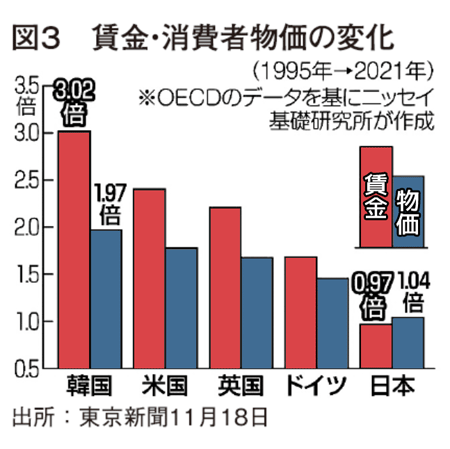
(図3・クリックで拡大します)
物価高の様相についてはすでに述べてきたが、厚労省によると9月の現金給与総額は9カ月連続で前年同月比を上回ったが、物価の伸びを差し引いた実質賃金は1.3%減と6カ月連続で下がった(この実質賃金の低下は、電車代や家賃など日常的には変化が少ない品目も含めた物価を反映している)。日銀は全国の4000人を対象に、1年前と比べて物価がどれくらい伸びたと感じているかを聞く調査をしている。回答の中央値を「体感物価」とみなし、みずほリサーチ&テクノロジーの酒井才介氏が「体感賃金」を試算したところ、7〜9月時点で前年同月比8.5%減となった。「日本のインフレは欧州の半分以下だ」と豪語した岸田首相、実態は欧州並みの生活悪化を強いられている。
23春闘に向けて連合は、「5%程度」(定期昇給分として2%含む)の賃上げ要求を掲げる。UAゼンセンは6%要求、全労連は「10%以上」を掲げる。「先進国並みの賃金水準」への達成の道のりは遠いが、近年の賃上げ率2%強を大きく上回る賃上げを実現させ、それを毎年続ける流れを作れるかどうかの岐路に立っている。最低5%の賃上げを何としても闘い取らねばならない。そのためには、17%弱の組織労働者の闘いから、未組織労働者を含めた全労働者の国民的な闘いへと発展させることが問われている。
本誌特集で、JAM労働組合の安河内賢弘会長が、「これまでは経団連や企業経営者に、我々の要求の根拠を必死で訴えてきたが、本当は、一般大衆、未組織労働者含めて『我々の要求は5%なんだ』と伝える努力が大切だ」と提起され、「今年の春闘は経営者に対して、ものわかりの悪い春闘にしよう」と呼びかけられている。
今闘わずして、何時闘うのか!
(11月22日)
|