|
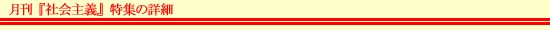
●2021年10月号
■ 衆議院選挙への課題を探る
宝田 公治
■ はじめに
9月3日、菅義偉首相が突如「次期自民党総裁選挙には立候補しない。理由は、新型コロナ対策も総裁選も大変なエネルギーが必要で、両立できない。新型コロナ対策に専任したい。これは国民の命と暮らしを守る首相の責務だ」と退陣を表明した。前日、二階自民党幹事長に続投を伝えていたにもかかわらずだ。首相に就任してから1年を待たず、安倍前首相に続き任期前に政権を投げ出した。本当の理由は、安倍前首相と同じく内閣支持率の低下、国民からの退陣要求である。北海道世論調査会によれば、内閣支持率:不支持率は、
- 昨年8月 安倍
- 支持38.6%:不支持51.1%
- 今年8月 菅
- 支持30.1%:不支持54.7%
退陣の理由は多々あるが、菅首相の場合は直後に総選挙を控えており、菅首相では総選挙は戦えないということだ。
菅首相退陣にいたるまでの迷走は、首相の座に居座り続ける執念のすごさをみる思いであった。それにもましてすごいと思ったのは、自民党の政権に居座り続けようとする執念である。その方法は評価に値しないが、政権を取るという執念は、野党に見習ってほしいものである。そして、これまたひどいのがマスコミ報道、とりわけテレビである。自民党といえども一政党の党内手続きにすぎない総裁選を取り上げる量の多さである。内容も派閥の動きがどうのこうのだとか、「国民的人気がある」「突破力がある」などの持ち上げ評論にはうんざりする。コロナ禍で国民の命と暮らしが脅かされている中で、6月10日通常国会を閉会して以来、開催されていない。それも7月16日野党4党が、憲法五三条にしたがって臨時国会開会を要求、それ以来再三要求を重ねているにもかかわらず、自民党は拒否し続けている。明らかに憲法違反である。こういう問題を大々的に取り上げるのが、マスコミの使命ではないのか。
そうした中で9月8日、ようやく野党四党の共通政策が実現した。いくつかの課題はあるが、これを基本に小選挙区での候補者の一本化をはかり、各政党が具体的政策をかかげ、比例区では切磋琢磨して戦い与野党逆転を達成し、その先の野党連立政権を念頭に戦う共闘体制が確立した。自公政権に対する選択肢ができたことの意義は大きい。
■ 安倍・菅政権9年の反憲法政治
昨年9月、自民党5派閥の推薦で自民党総裁になり、首相に就任した菅氏は「安倍政治の継承」「自助・共助・公助の政治理念」を表明。つまり新自由主義・強権政治を安倍政治から継承するとした。したがって、退陣の原因を究明するには、菅政権1年だけではなく、安倍政権からの9年間を分析する必要がある。
・新型コロナウイルス感染症対策
新型コロナは、地震などの自然災害とは違って、広義の意味でも人間行為のグローバル化等人災の面があるが、安倍・菅政権のコロナ対策は、狭義の意味でも人災と言わざるをえない。科学的知見によらない無為無策、後手後手の対応が国民の命と暮らしを脅かし奪っている。政治の役割は「公助を基本として、国民の命と暮らしを守る」ことであるが、安倍・菅政権は「自助」を優先し、国民に自己責任を押し付けてきた。具体的には、
- PCR検査など検査を拡充してこなかったこと。コロナ対策の基本は、無症状感染者の発見・保護(隔離)である。「いつでも、どこでも、何度でも、無料で」検査が受けられることである。それが、感染拡大を抑えている世界の主流でもある。
- 医療・保健機関を拡充してこなかったことが医療逼迫・崩壊、ひいては「原則自宅療養」という医療放棄をもたらしている。公的な医療・保健機関の整理縮小は、1991年中曽根政権以来の自民党による新自由主義・社会保障改悪、とりわけ2001年からの小泉政権によってもたらされ、安倍・菅政権に引き継がれたものである。今後は、地球温暖化による新型のウイルス・細菌感染症の発生を考慮した医療・保健機関の拡充が求められる。また、民間医療機関やその従事者に対して協力依頼をするならば、経済支援は欠かせない。
- 世論と逆行した「Go Toキャンペーン」「東京オリンピック・パラリンピック」の強行である。国民に行動の自粛を要請しながら、真逆の施策によって緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発令・延長の繰り返しになっている。さらに、現在は宣言中であるにもかかわらず、11月頃からの「行動制限の緩和策」公表は何をか言わんやである。総選挙目当ての「やってる感」を見せる姑息な手段としか言いようがない。このことは、ワクチン接種でも早め早めの予定を公表し、「やってる感」は見せるが結果はそうならず、国民・地方自治体に混乱を招いているが、その反省はない。
- 飲食店をはじめとして企業への自粛要請に対する経済支援が充分でない。自粛要請への経済支援、勤労国民・労働者の収入減に対する生活支援は基本である。
・民主主義否定の強権政治
上記でも述べたが、「Go Toトラベル」の一時停止の遅れ、「東京オリ・パラ」の強行実施などは、「国民の命を守れ」という世論を無視した強権政治だ。日本学術会議の会員任命では、学術会議が推薦した6人の任命を拒否し、理由は一切述べなかった。この6人は、安倍政権時代に憲法違反の安保法制等に反対した学者である。憲法二三条「学問の自由」を脅かし委縮させるものである。さらにいえば、一九条「思想・信条の自由」、二一条「言論の自由」にも反する行為である。
また、沖縄県名護市の辺野古新基地建設は、沖縄県民の民意に反して建設を強行している。
さらに、次期最高検察庁検事総長の人事を巡って、法律違反をおかしてまでも黒川東京高検検事長の定年を閣議決定で延長し、その後、検察庁法をそれに合わせて改正しようとした。このことは安倍政権による検察の支配であり、独裁政治の極みといっても過言ではない。ネット上で「検察庁法改正案に反対します」への賛同が、短期間で500万件を超え廃案に追い込んだ。また、黒川検事長は「賭けマージャン」が発覚し辞任に追い込まれた。
・政治と行政の腐敗
安倍前首相が関わる「森友」「加計」「桜を見る会」等国政の私物化は、安倍・菅両首相は「ていねいに説明する」と言いながら、世論は「全く説明できていない」と納得していない。これらの問題に関しては、国会での虚偽答弁、文書の改ざん・隠ぺいが横行し、それに関わった公務員が自殺に追い込まれても頬かむりのままだ。疑惑は全く解明されていない。
政治とカネをめぐる腐敗も後を絶たない。参院選広島選挙区での河井克行元法相・案里夫妻による大規模選挙買収事件では、案里氏が有罪確定、克行氏も一審で有罪判決を受け議員を辞職した。この事件に関しては、自民党本部から交付された1億5000万円が買収の原資になったかどうか、そもそも1億5000万円の原資はどこから出たのかも未解明のままだ。これ以外でも安倍・菅政権下で有罪判決によって多数が辞職に追い込まれている。最近では、いわゆる「カジノ事業(IR法)」をめぐり、秋元衆院議員が一審で実刑判決を受けた。すでに秋元議員は自民党を離党しているが、それで自民党が免罪符を得たと考えるならば言語道断だ。
官僚の政権への忖度は、官邸が幹部官僚の人事権を握る「内閣人事局」に問題があることは多くの方が指摘している通りだ。それに加え最近では、総務省・文科省の幹部官僚が利害関係にある業界から接待を受けるなど、腐敗は広がり深まっている。
・貧困と格差拡大
安倍政権発足の2012年と新型コロナ発生の前年2019年(または2018年)の主な指標を比較する。

(図表1・クリックで拡大します)
・比較分析の特徴点
- 実質賃金は低下している。2018年の国際比較(1997年を100)をすると、
- 日本92、
- イギリス193、
- アメリカ182、
- フランス169、
- ドイツ159
で、日本だけが低下している。1995年、日経連が打ち出した「新時代の日本的経営」は、非正規雇用を増やすという経営方針。以来、非正規雇用が増え、実質賃金低下の要因となっている。
- 雇用者数全体は増えているが、非正規が多い。非正規に女性の占める割合は68.1%と高い。コロナ禍でのしわ寄せは非正規が大きく、女性に集中している。
- 増加率は、利益剰余金(内部留保)53.1%や配当金88.5%に比べ、人件費6.6%は非常に少ない。それは労働分配率の低下▲8.3%に現れている。企業の利益が労働者に分配されていない。
- 以上も原因となり、生活保護世帯は5.1%増加している。小泉政権発足の前年2000年:75万世帯と比較すると、2倍以上の119%増と新自由主義の本質をよく現わしている。
・世論調査より
政権の評価を北海道世論調査会(新聞・テレビ局の世論調査の分析)の今年8月と昨年9月を分析すると、
-
- 菅政権発足時の内閣支持率
- 支持65.0%:不支持19.7%
- 今年8月支持率
- 支持30.1%:不支持54.7%
と大幅に下落している。
- 菅氏に首相を続けてほしいか
- ほしい26%・ほしくない63%
これが国民の評価である。
-
- 新型コロナへの政府の対応
- 評価する26%・しない64%、
- 緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の拡大・延長
- 効果ある22%・ない67%、
- 医療崩壊の不安
- ある80%・ない15%、
- ワクチン接種
- 順調23%・遅い72%、
- 東京五輪は感染拡大につながったと思うか
- 思う63%・ない32%
とコロナ対策は、評価されていない。
- 1月の調査では、
- 「桜を見る会」の安倍氏の説明は
- ――納得できる12%・不十分75%、
- 菅政権は政治と金の問題を改善できるか
- ――できる12%・できない81%
と疑惑の解明はされていない。
- 政党支持率(昨年9月→今年8月)は、
- 自民45.9%→34.4%
- 立民7.0%→7.5%
- 共産党2.9%→3.5%
- 社民党0.4%→0.3%
と自民党の支持率は低下しているが、野党の支持にはつながっていない。そして、自民党の総裁選で自民党の支持率は上昇するだろう。これに対するには、あらゆることで野党の一体化とその見える化が求められる。
■ 自公政権に対峙する野党共闘
・自民党総裁選|国民不在の権力闘争
昨年の総裁選とは全く様相を異にしている。昨年は安倍退陣後短期間で、5派閥が支持を表明した菅氏が圧勝した。しかし、今回は国民から「No!」を突き付けられた安倍・菅政権の民主主義否定の強権体質、そして当選3回以下を中心とする議員(「党風一新の会」など)が、派閥優先体制での総裁選に反発したことなどもあってか、会長が候補者である岸田派以外は「自主投票」と民主主義を装っている。しかし、河野氏支持を表明した小泉環境相が明かしたように、水面下では派閥の領袖が暗躍し、国民不在の権力闘争に明け暮れているのが実態である。コロナ禍で国民の命と暮らしが脅かされているなかでである。
原稿執筆時は、候補者4人が確定した直後だが、いずれも安倍・菅政権で政府や自民党で要職を担った人たちである。「ぬくもりのある政治を実現する」との主張だが、菅首相が主張した「安倍政治を継承して、国民に自助を求める冷たい政治」を支え推進してきた人たちである。その反省を全く顧みず、「国民に寄りそった政治を行う」などとの主張に騙されてはいけない。国民に寄り添った政治を取り戻すには、野党連立政権の樹立しかないのである。
・野党共通政策の実現
立憲民主党(以下、「立民」)、共産党、社民党、れいわ新選組の野党4党は、「安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合」(以下、「市民連合」)の「野党共通政策の提言(6つの柱・20項目)」に合意した。本来は、市民連合と4野党が対等の立場で、さらには国民民主党が加わった形での合意がベストではある。しかし今回の合意は、市民連合の山口二郎法政大学教授が述べているように、「本格的な野党協力の体制を確立できたことは、日本の民主主義を回復するための貴重な一歩」となったのである。
「市民連合の提言」は、前文で「自公政権の統治能力の喪失、政策の破綻は、安倍・菅政権の9年間で情報を隠ぺいし、理性的な対話を拒絶してきたことの帰結である。総選挙で自公政権を倒し、新しい政治を実現することは、日本の世の中に道理と正義を回復するとともに、市民の命を守るために不可欠である。市民連合は野党各党に共通政策を共有して戦い、共通政策を実行する政権の実現を目指すことを求める」とした。これに対し、野党各党首が「共通政策を共有し、その実現に全力を尽くす」として、市民と野党が同じ目的で統一して戦うという画期的なことである。
・共通政策の特徴
共通政策は、上述した「自公政権が実行しなかったことを実行する」、つまり「憲法を護り活かす」具体的な内容になっている。総選挙で野党連立政権が樹立されるならば、個人が大切にされる画期的な、いや歴史的な社会が実現されるであろう。具体的には「6つの柱・20項目」すべてであるが、特徴的なものをあげると、
- 「命と暮らし、人権」では
従来の医療費削減政策を転換し、医療・公衆衛生の整備を迅速に進める/非正規雇用・フリーランスの処遇改善により、ワーキングプアをなくす/消費税減税を行い、富裕層の負担を強化するなど公平な税制を実現する/差別を許さないため選択的夫婦別姓制度やLGBT平等法などを成立させる。
- 「環境、安全保障、政治のあり方」では
再生可能エネルギーの拡充により、原発のない脱炭素社会を追求する/安保法制、特定秘密保護法、共謀罪などの法律の違憲部分を廃止する/核兵器禁止条約の批准をめざす/辺野古での新基地建設を中止する/森友・加計問題、桜を見る会疑惑などの真相究明を行う/日本学術会議の会員を同会議の推薦通りに任命する。
■ 急がれる課題と闘いの認識
一つは、市民連合の山口氏が「共通政策を旗印に掲げ、野党連立政権をめざしていく。その枠組みは選挙結果を踏まえて考える他ないが、選挙を協力して闘う野党と市民の信頼感が新政権の重要な土台となる」と述べている。そのためにも、候補者の一本化を早急に実現することである。
二つは、今後共通政策に沿って各野党が独自の政策を作成する段階となる(既に作成済みもある)。各野党は違いを強調するのではなく、自公政権へ対抗する共通点を強調することが求められる。
三つは、連合本部が立民と共産党との共闘に批判的な言動を続けている。この克服のためには、地方における市民と労働者、野党の共通政策づくりと運動の強化が求められる。
以上述べてきた闘いが、矛盾を深める資本主義社会に代わる未来社会、つまり社会主義社会の実現=平和革命に向けた第一歩だという認識である。『社会主義協会の提言第1章第3節「国家権力の平和的移行」』は、「反独占、民主主義擁護、反帝国主義戦争の統一戦線の結成にむけて当面の課題を改憲阻止のための国民会議の確立強化におく。この組織化は、われわれの社会主義革命への道にとって、基本的な闘いである」としている。今回の野党共通政策の提言を実現することは、自民党による憲法破壊政治に対抗する「憲法を護り活かす」運動、闘いであり、『提言』の今日的適用ということではないだろうか。
(9月21日)
|