|

●2019年12月号
■ 全世代型社会保障改革に向けて
―― 社会改革の試み ――
平地 一郎
■ 社会保障改革の新しい潮流
社会保障の歴史は、
- 公的扶助、
- 保険原理
そして
- 普遍主義的福祉
へという流れに整理できる。これは、資本主義の悪弊に対する社会の復元力を示しており、窮乏化作用に対する反作用の変遷史と言ってよい。
貧困を慈善によって救済しようとする公的扶助(救貧法)の時代は、福祉を人々の権利として位置付けないため、その給付にはミーンズテスト(資産調査)を要件とし「劣等待遇」を基本とした。つぎに、19世紀末から20世紀初めにかけて勤労という事実を受給資格とした社会保険(保険原理)が登場し、自らの拠出が条件であることから、その給付は権利として位置付けられた。こうして福祉が権利となっていったものの、保険原理はすべての人々を包摂するものではなく、そうした人々を、保険の外側の公的扶助の対象とするか、あるいは保険の拠出に例外を設けるかによって対処せざるを得なかった。そして現代の新しい潮流は、市民権に基づく普遍的な給付(普遍主義的福祉)に重きが置かれている。
エスピン・アンデルセンは、「脱商品化」という観点から現代の「福祉資本主義」を3つに類型化している。表1のように、「自由主義的」、「保守主義的」そして「社会主義的」福祉国家である。保守主義的というのは、社会保険を基礎とする社会保障制度をとり、また社会(民主)主義的というのは、保険ではなく税を中心にした普遍的福祉政策をとるあり方をさしている。
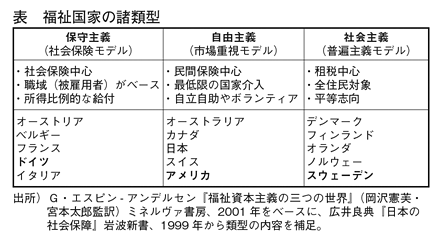
(図表1・クリックで拡大します)
おおよその言い方をすれば、先の社会保障の歴史における1.2.3.に相当する。
現代の普遍的な給付の典型的な例が、ベーシック・インカム論である。基礎所得と訳されることが多い。もとより、これは社会保障制度のすべてではないが、まずは、そうした普遍的な給付が現実にも可能であることを示しておきたい。あくまでも一例である。
すべての市民に対して、たとえば月額8万円の基礎所得を支給するとしよう。そうすると総支給額は、約120兆円(8万円×12カ月×1億2000万人)。現在の所得総額は約250兆円なので、その半分ほどが基礎所得として保証されるという計算になる。国民経済全体で見て、けっして不可能な制度ではない。
しかしこれほどの大胆な所得構造の改革となると、現在の制度から転換するには数十年を要すると言われる。社会保障改革は待ったなしである。そこで、わが国の特殊な状況も考慮して、5年〜10年という中期の期間で考えると、つぎのように組み合わせた制度の可能性が高い。なお、日本の特殊性とは皆保険制度の下で拠出の例外規定(免除制度)という構造である。免除の部分を基礎所得に整理して普遍的給付とし、保険による給付との2本立てにする。
すなわち、
- 子ども世代(基礎所得A)、
- 現役世代(基礎所得A + 勤労所得)、
- 老後世代(基礎所得B + 年金所得)
である。ただし、現役世代の基礎所得Aは当面ゼロから出発し順次導入・拡大する。
具体的な数字を当てはめてみよう。基礎所得A=月額4万円とし、基礎所得B=8万円とすると、さしあたり必要な基礎所得総額は、
- A=10兆円(月額4万円×12カ月×2000万人)
そして
- B=30兆円(月額8万円×12カ月×3000万人)
の合計40兆円となる。
現在でも基礎年金への税からの支出が12兆円ほどで、また生活保護の半数を占める高齢者の保護費は基礎所得Bに充当できる(合わせて約15兆円)。さらに法人税の重課税と所得税の累進課税を強化して25兆円を確保する。ここは大変だが、やり抜けば必要な40兆円に届く。
現役世代の基礎所得は順次実施し、その財源は、企業内福利費のうち退職積立金(引当金)など法定外の費目を充当する。これが約20兆円。企業による支出ではなく、社会が確保してそれによる支出に切り替える。老後世代と子ども世代の基礎所得を優先して、現役世代はその後の賃金労使交渉の結果を加味しながら、徐々に実施する。賃上げ分を基礎所得に回すのも一案である(春闘改革)。
もとより、これらの数字にはさまざまな留保が付くし、また実現するための工程表も必要である。たとえば、移行期には、
- 老後世代の基礎所得Bは、保険料を支払ってきた場合は8万円+2万円を基礎所得として、10年後にはすべて10万円に統一する、
- 困窮・障害・失業等を対象とする特別所得(基礎所得B+α)も並行する
……等々である。
ともあれ、本稿の目的は、制度設計の詳細を提案することではないので、これにとどめよう。
基礎所得制度は、シティズンシップ(市民であることそのもの)に基づいて構想される権利体系の一例である。給付によるのではなく、各世代、各人のニーズに沿ったアクセス権として保証する諸施策の形成など様々なバリエーションは考えられる。いずれにしても、市民権に基づいた協力(支え合いの)関係の視点から、子育て・医療・介護・年金等の社会保障制度を構築していくことが「全世代型」の意味するところである。
本稿はそうした視点から、アベの「全世代型社会保障」を考える。
■ 全世代型社会保障はどう語られてきたか
アベ政権が「全世代型社会保障」の方針を打ち出したのが、2017年10月の総選挙である。その2年後の10月には消費税を10%へ引き上げることから、それを財源とした方針であった。そして、2019年9月18日「全世代型社会保障検討会議」が開催された。
こう見ると、全世代型社会保障はアベの専売のようだが、じっさいには、麻生内閣そして民主党政権の時代に登場し形成された考え方である。
2009年6月の「安心社会実現会議」報告は、「安心社会の実現のためには、高齢者支援を引き続き重視しつつも、若者・現役世代支援も併せて強化しながら、全生涯、全世代を通じての『切れ目のない安心保障』を構築する」とした。
そしてその後、民主党政権の下で議論が進められた社会保障改革国民会議の最終報告書(2013年8月6日)は、「将来に対し、夢と希望を抱くことができる社会保障を構築することによって、若い人々も納得して制度に積極的に参加することができる。こうした観点から、若い人々も含め、すべての世代に安心感と納得感の得られる全世代型の社会保障に転換することを目指し、子ども・子育て支援など、若い人々の希望につながる投資を積極的に行うことが必要である」とした。
2013年8月の最終報告書は、その前年の自公民3党合意(税と社会保障一体改革)における消費税増税を前提として構想されており、その限りでは、現アベ政権が10%に消費税を引き上げるタイミングで「全世代型社会保障」を前面に出すのは不思議ではない。しかし2016年4月の消費税8%への引き上げの際にもその施策を実施すべきとされていたにもかかわらず、アベ政権はまったく無視していたといわれる(『世界』2018年2月号)。
つまり、アベの政策のなかでは「全世代型社会保障」はそもそも位置を与えられていなかったのである。ところが「アベノミクス」が頓挫する2017年以降、野党の政策の言わばパクリが始まる。野党提出の「同一労働同一賃金法案」を否決したあと、すぐにアベは「同一労働同一賃金」を語り出し、そして全世代型社会保障を打ち出した。なりふり構わない「抱きつき戦術」と揶揄された先に、2017年10月総選挙のアベの勝利があったことになる。
さて、社会保障改革国民会議最終報告の積極的な内容を紹介しておくべきであろう。この報告書は、消費税増税を前提としていたこと、また公表がアベ政権誕生直後であったことなどから、いくぶん軽く扱われていたきらいがある。とはいえ重要な報告書である。少しばかり私の補足も入れて内容を敷衍すれば、つぎの二点である。
第一に、社会保障の意義が、世代間の対立としてではなく、社会的な支え合いとして強調されている。高齢者に対する年金制度についてみれば、たしかに現役世代の拠出を主な財源とする。しかし従来の家族関係の下では、老親は子の扶養のなかにあって、それなりの負担支出を行っていたのであり、それを社会化して支え合うのが年金制度である。公的年金制度が現役世代の負担を増やしているわけではない。
第二に、社会保障改革が全世代の課題であることも強く意識されている。介護についてみれば、従来の家族関係の下では、現役世代の子の義務とされ、その担い手は、男性稼ぎ手モデルにおける専業主婦にとどめ置かれた女性であった。しかし今日、男女ともに仕事を持つという現実のなかでは、介護が社会化されなければ、現役世代と老後世代は共に倒れる。また、少子化の背景は、長期的には女性を育児の担い手としてきた男性稼ぎ手モデルの変容であり、中期的には若者から結婚・出産・育児のための条件を奪った1990年代以降の雇用形態の変化すなわち非正規化であるが、これに対して子ども・子育てを支援するシステムの構築を含めた全世代対応の社会保障制度改革が急務である。
こうした考え方から、全世代型社会保障改革を構想したのが、2013年8月の社会保障改革国民会議最終報告であったと言ってよい。
では、アベ政権の「全世代型社会保障」は何を語ろうとするのか。
■ アベ政権の抑制政策と全世代型
なによりも先に検証しておかなければならないのは、アベ政権が、社会保障をどう扱ってきたのかという問題である。それは、一言で言えば、社会保障費を削減しようとする姿勢である。
アベ政権は、毎年の予算編成過程で、社会保障費の自然増分を大幅にカットしてきたが、その削減額は2013年度以降の6年間で1.6兆円にのぼると言われる。また、社会保険料(年金・医療・介護)の引き上げ、給付要件の厳格化、患者・利用者の自己負担の増加など図られ、こうして「いま、日本では、社会保障費の抑制・削減が進められ、国民生活がますます苦しくなり、将来への不安が増大している」(伊藤周平『社会保障入門』2018年、ちくま新書)。
なかでも、アベ政権下で目立つのは、生活保護世帯に対する支給の削減である。2013年と2018年の2回にわたって、生活保護基準の減額の方向への見直しが行われている。
- 2013年8月から生活保護のうち食費等に充当される生活扶助の支給額を6.5%削減(削減額580億円)。その削減額は戦後最大と言われる。経緯はつぎの通りのようである。
「厚労省がこの削減方針を固めたのは13年1月。12年12月、生活保護の給付水準の原則1割カットを公約に掲げて自民党が政権復帰した翌月のことだ」(朝日新聞、2019年10月14日付け)。
- 2018年10月からは、おおよそ7割の保護世帯の受給額を減額した。とくに、子育て世帯や母子世帯の減額率が約5%と高い。生活保護費を3年かけて段階的に引き下げ、年に160億円(1.8%)削減するとした。
こうした社会保障費の削減の背景には、この間のアベ政権の「歳出改革」がある。
2015年6月の「経済財政運営と改革の基本方針2015」(閣議決定)は、歳出改革の項においてつぎのように述べている。
「社会保障は歳出改革の重点分野である。社会保障給付の増加を抑制することは個人や企業の保険料等の負担の増加を抑制することにほかならず、国民負担の増加の抑制は消費や投資の活性化を通じて経済成長にも寄与する。社会保障改革を進めるに当たっては、それが、次世代に社会保障制度を引き継ぐ改革であるとともに、国民負担の増加の抑制を図るものであることについて広く国民の理解を得ながら着実に改革を進める」。
すなわち、社会保障費の抑制こそが歳出改革の中心であるというのである。社会保障費を抑制すれば、国民負担が減少し、消費や投資が拡大することで経済が成長するという不思議な論理―非論理的論理―がそこにはある。社会保障費は確実な消費支出になるのではないのか。
「社会保障費給付の増加の抑制」は、その後一貫して追求されてきた政策である。それから3年。2018年3月の「経済・財政一体改革の中間評価」は、先の「歳出改革の計画」を振り返りながら、「国の一般歳出、社会保障関係費の伸び、地方の一般財源総額についての目安を定めて歳出の効率化に取り組み、集中改革期間の予算編成においては、……それぞれ目安に沿った予算が編成された」とアベ政権の成果を高く評価した。
この「中間評価」は、今後についても言及している。社会保障関係費の自然増は続くと見込まれるとして、これを抑制するために「全世代型社会保障制度の構築に向けて取り組んでいくことが重要である」としている。そのポイントは、「給付と負担の適正化」という名の負担増であり、社会保障分野における再編整備・生産性向上による「効率的な提供体制」の推進である。
このようにアベ政権の社会保障政策は、もっぱら「財政上」の問題として、すなわち削減の対象として位置付けられてきたと言ってよい。そして、突然の全世代型の提唱も、そうした文脈のなかにある。
そもそもアベの全世代型社会保障改革は、その理念に共鳴しての提唱ではない。その背景には人々の不満があるとの認識がある。2017年10月の総選挙後の経済財政諮問会議(10月26日第14回)における安倍首相の発言はそれを窺わせる。
当初、消費税増税分は「財政再建」に充てる予定であり、2013年の「社会保障改革国民会議報告書」は念頭に置かれていなかった。しかし、この間の社会保障費抑制が国民の反発を買っているとの認識はあった。「小泉政権時代、私――安倍――は官房副長官、官房長官で、一緒に進めたのが2200億円削減を5年間進めるというものである。我々がカットしたものの半分以下だが、ものすごい反発があって、結局、結果として、社会保障関係費について5年間という目標の3年間も達成できなかった。……その点はよく考慮していただきたい」。ただし、「財政再建の旗は降ろさない」。
すなわち、国民の反発があるので「子育て世代への投資と財政再建」とに半分ずつ充当することにしたという安倍首相の「政治的配慮」が明瞭に語られている。けっして全世代型の理念に基づくものではないのである。
この間、高校授業料の無償化には所得制限が設けられ(2014年)、また来年から始まる大学の授業料無償化も所得制限が入っている。アベ政権の下で普遍的福祉の理念は損なわれている。「無償化」の言葉だけが踊る。
財政再建と全世代型との、一見すると相容れない関係は、経済財政諮問会議での議論及び委員からの提言等を見ると、つぎのような帰結へ至ると思われる。
第一に、社会保障費は、税・保険料・利用者負担からなるが、税は増税するとすれば消費税。保険料は使用者拠出分があるので拒否。残るは利用者負担の引き上げ。第二に、社会保障費のうち医療・介護は、民間による供給なので、その供給価格の低廉化。あるいは、供給体制のコストダウン。第三に、年金については、マクロ経済スライド。その他に、受給開始年齢の引き上げと保険対象者の拡大。
社会保障費を削減するとすれば、医療・介護分野での利用者負担増及び支出抑制が本丸である(第一及び二)。
第一の点は、医療における患者負担の検討として始まっている((1)75歳以上の窓口負担を1割から2割への引き上げ (2)外来受診時の定額負担の導入 (3)市販薬のある場合の保険対象からの除外)。これに対しては医師会・歯科医師会・薬剤師会から反対が出されているが、もちろんこの議論は、全世代型とはまったく関係がない。高齢者にも現役世代と同じ3割負担へというものであり、医療に対する必要性の意味が考慮されていない。また、現役世代も将来は高齢者になるのであって、世代間対立として負担増を正当化しようとするのは、全世代型社会保障の理念に反する。
同様の問題は、介護の利用負担をめぐっても展開されていくだろう。
第二の点は、医療・介護の「供給体制」を合理的なものにするという意味であれば、議論されてよい(多剤投薬の抑制、ジェネリック医薬品の普及など)。
わが国の医療制度は、供給側の中心に民間病院(開業医)がいるという特徴がある。公的病院(例えばイギリスは公営病院で医師等の医療従事者は公務員)が税あるいは保険料を元にして制度設計されているヨーロッパとは違って、日本では民間病院が医療を提供する。したがって、本来の改革は医療を如何に社会的・公的な要請に沿って編成していくかであろう。しかしながら、アベの政策は社会保障費の削減(安価な医療供給)に偏っており、人々のニーズに応えることはできない。
今後の全世代型の議論は、2019年末までに年金・介護、2020年度の「経済財政運営と改革の基本方針」までに医療等を含め、給付と負担のあり方を見直す総合的な社会保障改革の政策をまとめるとしている(2019年6月「骨太の方針」……全世代型社会保障検討会議への提出基礎資料)。議論は始まったばかりであるが、利用者負担増、保険対象拡大、安価な福祉供給という提案が目立つ。
従来の社会保障制度の手直しの議論ではなく、私たちの側の(松尾匡氏の表現を借りれば左派の)社会保障政策を大胆に提起する必要があろう。本稿は、そのための資料的試案として、普遍的福祉への転換及び2013年8月の社会保障改革国民会議最終報告書における「全世代型」の再評価を強調したい。
(2019年11月16日 記)
|