|

●2019年1月号
■ ゴーン逮捕と外国人労働者の拡大
立松 潔
■ ゴーン逮捕の衝撃
日産のゴーン会長の逮捕はビジネスエリートの強欲さと高報酬の問題に多くの国民の目を向けることになった。逮捕されたのは昨年(2018年)の11月19日、容疑は金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)である。2010〜14年度の5年間の報酬が実際は約98億5500万円だったにも関わらず有価証券報告書には49億8700万円しか記載しなかったというものである。なお、有価証券報告書に記載された額との差額は別名目で蓄積し、退任後に一括受け取ることになっていたという。
その後東京地検特捜部は2015〜17年度の3カ年分についても過少に記載されていたとして、12月10日にゴーン氏を再逮捕している。この3カ年分の報酬は実際は71億7400万円だったのに有価証券報告書には計29億400万円と過小に記載されていた。
1998年6月に日産自動車のCOO(最高執行責任者)に就任したカルロス・ゴーンは、99年10月に再建計画「日産リバイバル・プラン」を発表。日産グループ全体で従業員2万1000人(全体の14%)の削減と、系列部品メーカーの切り捨てによる部品購入先(当時1200社)の半減という大リストラを敢行した。その結果、日産の経営はV字回復し、ゴーンは日産の救世主として、グローバル時代の経営者の鏡であるかのようにもてはやされたのである。犠牲になった労働者や下請け企業の気持ちは一切顧みられることはなかった。そして98年12月には346円(終値)だった日産自動車の株価は2002年の12月には926円に回復し、株主を喜ばせた。
企業の利益を増やし株価を引き上げ株主のために貢献した経営者は(業績連動型の)高額報酬を手にするのが当たり前というのがアメリカ的経営の考え方である。ゴーンは当然のごとく高報酬を要求し、こうして公表額で年10億円もの報酬を得ることになった。しかし実際の報酬はその倍以上だったことが今回明らかにされたのである。
■ 日本的経営の変質とゴーン改革
1990年代は日本的経営が大きく変質した時代であった。それ以前の日本的経営では、不況で減益になっても人員整理は極力控え、長期的視点から人材を温存するのが当たり前とされていた。解雇やリストラは会社の存続が危うくなるギリギリの「最後の手段」と考えられてきたのである。アメリカ企業のように、不況になると「最初の手段」として人員削減を行い、早期に採算を改善させようとする経営とは大きな違いであった。そして80年代までは、このような人材重視の経営こそが日本企業の強い競争力の源泉であると信じられていたのである。
しかしバブル崩壊後の不況が長引く中で、過剰人員を抱え続けて利益を食いつぶす日本的経営に対する株主からの批判が強まり、日本企業もアメリカ的な株主優先経営への転換が進むことになる。1995年には日経連が「新時代の『日本的経営』」という有名な報告書を出し、正規雇用の削減=少数精鋭化と非正規雇用の活用による人件費削減の方向を打ち出した。そしてこれ以降デフレ不況の深刻化のなかで企業のリストラが急激に進行する。そしてその際の見本となったのが日産におけるゴーン改革であった。
こうして労働者の賃金が抑制される一方で、役員報酬は引き上げられ、企業内の所得格差も急速に拡大することになる。図表1はバブル期と小泉政権下の景気拡大期における大企業の付加価値の分配を比較したものである。バブル期には株主への配当はほとんど変わらないのに対し、役員報酬と従業員給与への分配はいずれも20%前後も増加していた。これに対し2001〜06年になると、従業員給与は削減され、代わりに株主への配当と役員報酬が著しく増加していることがわかる。また、東京商工リサーチの「役員報酬1億円以上開示企業調査」によれば、報酬が1億円以上の役員の数も開示が始まった2010年3月期には289人であったが、2018年3月期には538人へと増加し、過去最多を記録している。
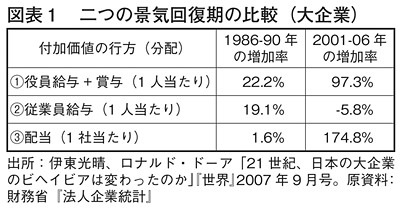
(図表1・クリックで拡大します)
しかし、アメリカにおいても特にリーマンショック後は経営者の高報酬に対し批判が強まっている。米労働総同盟・産別会議(AFL|CIO)も経営者のお手盛りによる高報酬を批判し、その抑制と従業員賃金の引き上げとを要求している。また、欧州では従業員と経営者の待遇に公平さを求める傾向が強いと言われており、役員報酬も(日本企業よりは高いものの)アメリカと比べればかなり低めである。米企業のトップの役員報酬の中央値が16.8億円であるのに対し、英独仏は3〜6億円台程度であるという(朝日新聞2018年11月28日)。
カルロス・ゴーンはフランスのルノーの会長兼CEO(最高経営責任者)であり、ルノーから直近の2015〜17年にいずれも年約9億円の報酬を受け取っている。しかし、株主から高額報酬に対する強い批判があり、2016年4月のルノーの株主総会では54%の株主が高額報酬に反対したという。議決に拘束力がないため予定通り支払われたものの、このような強い批判にたいし、日産からの報酬が別に20億円もあるということは公表しづらく、それが報酬の半分を隠蔽した理由ではないかと言われている(朝日新聞18年12月4日)。
しかし、グローバル化への対応を理由に日本の役員報酬をさらに引き上げるべきという主張も国内の経済界やマスコミでは依然根強いものがある。たとえば「日本経済新聞」のゴーン逮捕に関する解説記事は次のように述べている。
「日産自動車元会長カルロス・ゴーン容疑者の問題を受け、高額批判も出ている役員報酬。ただ、主要企業のトップの報酬を比較すると日本は米国の1割程度にとどまり、国際的には低い水準にある。経営者も含めた人材獲得のグローバル競争で後れを取る恐れがある。」
「外国人も含めて優秀な経営者を引きつけるには、日本の役員報酬は欧米に見劣りしない水準へと切り替わっていく必要がある」
(18年12月1日 日本経済新聞電子版)
しかし、アメリカと日本では役員の構成が全く異なっている。日本では社員が(出世競争を通じ)内部昇格で経営トップに上り詰めるケースが一般的である。これに対しアメリカでは高額報酬を求めて企業を渡り歩くプロ経営者が多く、企業は競ってそのような外部人材を雇い入れることで報酬額の高騰が引き起こされている。
外部人材を引き抜くために高額報酬を用意するのは現に日本でも行われているし、最近ではそういうケースが増えているという。しかし、それに併せて内部昇格の役員の報酬まですべて欧米並みに引き上げろとでもいうかのような「日経新聞」の主張は、経営者のお手盛りによる高報酬を奨励するものでしかない。これでは役員報酬引き上げの財源確保のために、従業員の賃金が抑制され、格差の一層の拡大を引き起こすことになりかねない。
■ 人手不足下の賃金低迷
最近の日本経済の大きな問題は、人手不足が深刻化しているにもかかわらず、それが賃金の上昇に結びついていないということである。厚生労働省『毎月勤労統計調査』によれば、2017年時点での実質賃金は安倍政権発足前の12年(5年前)と比べ4.1%も低く、リーマンショック前の07年(10年前)より7.7%低い水準にとどまっている。
2018年版の『経済財政白書』では内閣府が行った「働き方・教育訓練等に関する企業の意識調査」の結果を紹介している。それによれば、
人手不足への対応策として最も回答の多かった選択肢は「採用手段多様化」で48%、
次が「人材育成による生産性向上」で41%、
3番目が「採用対象の拡大」(32%)、
4番目が「従業員の残業・休日出勤」(24%)で、
「賃金等待遇改善による繋(つな)ぎとめ」は5番目で19%に過ぎない。
なお、6位以下は
「省力化投資」(19%)、
「業務量の抑制・受注調整」(12%)、
「営業時間の短縮」(6%)
となっている。衝撃的なのは、残業・休日出勤など従業員の労働時間延長によって人手不足を乗り切ろうとする企業が24%と、賃上げや待遇改善による対応(19%)を上回っていることである。
多くの日本企業は、労働条件切り下げが日常化する長期のデフレ不況を経験するなかで、ブラック的な体質がしみつき、経営が改善した人手不足下においても賃金など労働条件の引き上げに消極的になっている。労働組合の組織率が低下し、賃上げを要求する労働組合の闘争力が弱まっていることも、企業にそのような選択を可能にしているのであろう。
以上のような状況に対し、安倍政権は財界に直接賃上げを働きかける「官製春闘」を演じるとともに、労働力不足への対応策として「一億総活躍」のスローガンの下で、女性や高齢者の就業促進を図ってきた。また2017年に打ち出された「生産性革命」も、その大きな狙いは省力化投資により人手不足を緩和することだったのである。
しかしながら、人口減少下の景気回復により、労働力不足は深刻の度を増すことになる。2018年10月時点の有効求人倍率(全国)は全体で1.40倍であるが、建設は4.96、介護サービスは4.18、接客・給仕が3.92など、一部の業種では人手不足が極めて深刻な状況となっている。労働局への労働相談でも、「退職したいのにやめさせてもらえない」というような、自主退職についての相談が増えており、本人に代わって退職を会社に伝える「退職代行業者」まで登場し、繁盛しているようである。
■ 外国人労働者の拡大を急ぐ安倍政権
このような状況のなかで安倍政権は、従来の方針を大きく転換し、外国人労働者の受け入れ拡大を人手不足対策の大きな柱の1つとして打ち出すことになった。これまで就労資格を与えられている外国人は医師や弁護士など「高度な専門人材」に限られていたが、今回それを大幅に緩和し、ほとんど単純労働者に近い外国人労働者の受け入れに踏み切ったのである。
人手不足の業種に外国人労働者を導入できれば、企業は賃金等の待遇改善策を実施しなくても存続が可能になる。そういう人手不足企業からの強い要望に応えることで、19年の統一地方選挙と参議院選挙を有利に進めようと、安倍政権はなりふり構わず外国人労働力拡大へと邁進することになったのである。
こうして外国人労働者の受け入れ拡大に向けた出入国管理法改正案が11月2日に閣議決定され、わずか17時間の審議で衆院を通過し、12月8日未明には参院で可決され成立することになった。安倍首相が法案の検討を関係閣僚に指示した2月20日の経済財政諮問会議から、わずか10カ月弱であった。国会での質疑を異例の短さで切り上げ、強引に押し切った結果である。こうして新しい在留資格による外国人労働者の受け入れが、今年(2019年)の4月から始まることになる。
新たな在留資格とは基本的な技能をもつ「特定技能1号」と、熟練した技能を持つ「特定技能2号」の新設である。特定技能1号は滞在期間が5年間に限定され、家族帯同は認められない。対象業種は介護、外食、建設、飲食料品製造業など14業種、受け入れ人数は初年度最大4万8000人、5年間で約34万5000人だという。
特定技能2号の場合は期限の更新による長期滞在が認められ配偶者や子どもの帯同も可能である。しかし、自民党内の保守派から「永住につながる移民政策」との批判を受け、限定的にしか認めないとの方針に転換された。当面は「特定技能1号」の運用状況を見守るということで、受け入れは数年先送りされ、人数も示されていない(朝日新聞18年11月22日)。
■ 人権無視の技能実習生制度
今回の外国人労働者受け入れ拡大に関する国会審議で問題とされたのが、外国人技能実習生が置かれた苛酷な労働実態である。厚生労働省の「『外国人雇用状況』の届出状況」によれば、技能実習生は2013年の13万6608人から17年の25万7788人へと4年間で1.9倍にも増加し、外国人労働者総数(127万8670人)の20%を占めるにいたっている。
技能実習制度は、発展途上国の「人づくり」に寄与するという国際協力の推進のために1993年に制度化されたものである。来日した実習生に日本の現場の技能、技術や知識を、日常の労働を通じて学んでもらい、それを自国のために生かしてもらうというのが本来の目的である。
しかし実際には不足する労働力を埋めるために技能実習制度が利用されてきたのである。この制度本来の目的に反し、技能の教授や育成が実施されない仕事に従事させられている事例も少なくないという。
このような中で、労働力不足に悩む受け入れ企業の側からは、最長5年の技能実習期間を終えた実習生が帰国してしまうことに不満の声が上がっていた。そこで政府は今回の新たな在留資格でそのような企業の要望に応え、3年間の経験がある技能実習生は特定技能1号への移行ができることにしたのである。政府は特定技能1号の受け入れ人数の50〜60%が技能実習生からの移行組になると見込んでいる。
しかし、多くの技能実習生が劣悪な労働条件のもとで人件費の安い労働力として酷使されていたという事実も、今回明らかにされた。技能実習生は他業種への転職や宿泊場所の選択の自由がないため、最低賃金以下での長時間労働を強いられても我慢して働かざるを得ない。また、多くの技能実習生が借金により保証金または不明瞭な手数料などを母国の送り出し機関(ブローカー)に支払っており、途中帰国するとその返済が困難になるため、劣悪な労働条件や人権侵害をも受け入れざるを得ない状況であった。技能実習生の失踪者数は2017年に7089人、18年上半期には4279人にものぼっているが、その背景には、以上のような苛酷な実態があったのである(※注)。
■ 外国人労働者との共生と労働条件の改善へ
実習先を変更できない技能実習生とは異なり、新設される在留資格による外国人労働者は、居住地や職場の変更が可能である。しかしながら、日本への渡航にあたって現地の送り出し機関から借金をせざるを得ない状況は技能実習生と同様であり、そのような弱い立場の外国人労働者に果たして日本人と同等の労働条件が保証されるかどうかは大いに疑問である。
そもそも積極的に外国人労働者を受け入れようとする企業には、日本人労働者が集まらない劣悪な労働条件のところが少なくない。今回の外国人労働者受け入れ拡大策はそんなブラック企業を延命させることにもなりかねないのである。
外国人労働者の劣悪な労働条件を野放しにすれば、日本人労働者の労働条件の改善も困難になる。外国人労働者に日本人と平等な労働条件が確保されるよう、処遇改善に向けた活動を進めることが求められている。そして、企業役員に対するお手盛りの高報酬をチェックするとともに、外国人労働者も含めた全労働者の労働条件の改善が、深刻化する格差拡大を食い止めるためにも不可欠である。
(※注)
法務省はこれまで、技能実習生の失踪の87%は「より高い賃金を求めて」の失踪だったとしていたが、今回衆参法務委員会の野党委員が失踪技能実習生に対する2017年の法務省調査の聴取票を分析したところ、その68%が最低賃金割れだったことが明らかになった。
|