|
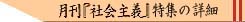 |
|
|
|

●2006年1月号
■ 年頭に当たって――小泉改革の「虚と実」
(小島恒久)
■ 小泉劇場のデマゴギー
2005年の流行語大賞に「小泉劇場」というのが選ばれた。それほど先の総選挙での小泉首相のスタンドプレーは目だつものだった。争点を郵政民営化一本に矮小化し、それに反対する者に造反者というレッテルをはって「刺客」を送りこむ。そして「改革を止めるな」をスローガンとして、「断乎」「決然」「命をかけて」といった悲壮な短語を連発する。それをマスコミもまた面白おかしく報道する。こうした小泉劇場を見て、日ごろ閉塞状況下にあり、やり場のない不満を抱いている多くの無党派層が喝采をおくる。これらの層は、小泉の言う改革では決して良くはならないのに、「改革」という名の幻想にひかれて小泉党に投票する。こうした大衆の心理にうまくつけこむポピュリズム(大衆迎合)政治に小泉はきわめてたけている。
その結果、小泉自民党が圧倒的な大勝を博した。そうなると、これまで造反していた議員までが、無節操にも、寄らば大樹の蔭とそれになびく。こうして小泉に反対する者がなく、言論が統制されたような政治状況が出現することになった。そこには、「新体制」の名のもとに大政翼賛会政治が出現した戦前の状況を思わせるような不気味さがある。
だが、この小泉劇場には非常なデマゴギーがある。「改革」という言葉だけでは何も説明したことにはならない。戦前のファシズムですら口では「革新」ということを唱えた。問題はその中身にある。たとえば今度の総選挙で小泉が一大争点とした郵政民営化では、「官から民へ」ということをさかんに強調した。一見ソフトなこのスローガンでいう「民」の中身は、しかし、一般国民ということではない。あくまで民間企業、とくに大企業ということである。だが一般大衆は、「民」といわれるとつい自分のためになるように錯覚させられる。こうした言葉のすりかえ、ごまかしが小泉改革では随所にみられる。だから、その欺瞞性をあばき、内実を明らかにすることが、われわれにとって重要な課題になる。この課題にこたえるべく本誌はこれまで努めてきたし最近の11月増刊号でも、「この間の構造改革の検証」という特集がくまれている。くわしくはそれらを参照していただきたいが年頭に当たり、ここでも小泉改革の「虚と実」を大綱的にふりかえっておきたいと思う。
小泉内閣は「聖域なき構造改革」というスローガンをかかげて、この五年間いろんなことをおこなってきたが、その基本方針を策定し、推進役となったのは「経済財政諮問会議」であった。これは小泉首相を議長とし、関係閣僚、日銀総裁のほか、民間議員として財界人2人、学者2人が入っている(労働界代表は入っていず、労働者の声は全く反映されない)。財界人は日本経済連合会会長の奥田碩(トヨタ)とウシオ電機の牛尾治朗であり、ともに独占資本のドンである。この財界代表が種々の提言をおこない、審議をリードする役割を果たした。そしてこの審議会が毎年「骨太の方針」という基本方針を出し、それにもとづいて構造改革はおしすすめられた。
この小泉改革でおこなわれてきたことを、ここでは大きく3つの柱に整理してみてみよう。
まず第一は、改革の初期以来強調された不良債権の処理である。この不良債権はもともと1980年代後半の金融超緩和政策のもとでおこなわれた銀行の野放図な貸しつけと、それを借りた企業の投機的な財テクの結果として生まれたものであった。このバブルのつけとして発生した不良債権を、金融機関は直ちに処理するということをせず、経営者の責任のがれのために隠蔽し、ごまかそうとした。またそれを監督する立場にある金融当局もそれを黙認するという事なかれ主義をとったので、この処理がずるずると遷延され、禍根としていつまでも残りつづけた。
しかも、この不良債権をかかえる金融機関救済のため、政府は超低金利政策をとり、公定歩合を0.1%という史上最低の水準まで下げた。これにともなって銀行の預金利子も下がり、貸し付け利子との利ざやが業務純益となって、銀行の懐をうるおした。これは銀行に預金している一般庶民の懐から、銀行への巨額な所得移転である。この一般庶民を犠牲にした金融機関救済策に依拠して、金融機関はまた不良債権の処理を怠った。
だが、この不良債権をいつまでも放置しておくというわけにはいかないので、小泉改革では――とくにその初期には――その処理の加速が大きな課題となった。そのため、金融庁が特別検査を強めて、不良債権を洗い出し、その処理を金融機関に迫った。金融機関は自らリストラを図るとともに融資先企業からの不良債権の取り立てを厳しくした。その過程で多くの金融機関や、返済不能の企業が破綻をよぎなくされた。破綻しない金融機関や企業でも厳しいリストラ合理化が強いられた。こうした破綻やリストラ合理化は、そこで働く労働者に、解雇その他の厳しい犠牲を強いられるものであった。
一方、この不良債権の処理と併行して、中央でも地方でも、銀行の合同合併が促進され、体質強化が図られた。とくに中央では大手金融・銀行グループへの集中化が進展した。そしてこれら大手金融・銀行グループは、不良債権の処理を一応終え、景気回復の追い風もあって、2005年9月の中間決算では、過去最高の利益を記録するにいたった。こうして金融面での独占体制の再編・強化が着々とすすんだのである。
■ 独占本位の構造改革
小泉改革の中軸ともいえる第二の柱は、経済構造改革であった。この改革の基調をなしたのは、市場の法則と競争原理を重視する「新自由主義」である。もともとこの「自由主義」というのは、産業革命によって資本主義が確立し、資本主義経済が最も典型的に花ひらいた時期の政策である。この本来の自由主義と、今日の新自由主義との最も大きな相違点は、独占の支配という所にある。かつての自由主義の時代には、相似たような規模の企業がお互いに競争しあった。ところが今日の新自由主義の場合は、一方で大企業、独占資本があり、他方には中小零細企業があるという不均等な状況下での競争である。となると、そこではきわめて冷酷な競争が展開され、強者が弱者を食っていく。その意味ではこれは強者の論理であり、強者、独占資本を利する改革である。
この新自由主義にもとづいて、まずおこなわれたのは規制緩和、すなわち市場の自由競争を阻害している規制を緩和することであった。たとえば、これまで独占の弊害を除去するために独占禁止法で一定の規制がおこなわれていたが、これを改正して、従来禁止されていた持株会社(ホールディングス・カンパニー)が認められるようになった。この結果、独占資本の活動がやりやすくなり、これを利用して企業の合同・合併がどんどん進行することになった。また商法などが改正されて、企業の分割・分社化などが容易になった。こうして企業、とくに独占資本をしばっていた縄がつぎつぎに解かれ、活動の余地がひろがって、独占の支配が着々と進展していった。
この規制緩和はいろんな方面でおこなわれたが、労働面でもすすんだ。これまで労働者が労働運動をつみ重ねてかちとってきた権利や保護は資本にとっては邪魔、規制とうつる。だから、規制緩和という名のもとに労働基準法などが改悪されて、この権利や保護がとり除かれていった。たとえば、女性労働者にたいする保護がとり払われた。変形労働時間制や裁量労働制で労働時間が弾力化され、超勤費が削減された。また労働者派遣法が改悪されて、派遣労働者の使用が大幅に拡大された。
こうした労働者の規制緩和によって、解雇が容易になり、また雇用の多様化がすすんだ。そしてパートタイマー、アルバイト、派遣労働者、契約社員、嘱託などの非正規雇用がいちじるしく増え、全労働者の3割を占めるようになった。しかもヨーロッパと違い日本ではこれらの労働者にたいする均等待遇制度が非常に遅れているので、これらの非正規労働者の賃金はきわめて低く、雇用も不安定である。この低賃金で不安定な雇用の増大が、「少子化傾向」の土台ともなっている。
このように資本の利潤追求活動を容易にする規制緩和を各方面でおしすすめるとともに、また小泉改革では、「小さな政府」をめざし、「官から民へ」をスローガンとして、民営化が推進された。この民営化はすでに1980年代の「行政改革」のとき国鉄、電々公社、専売公社などでおこなわれた。今回のばあいは道路公団、なかでも先の総選挙で一大争点とされた郵政の民営化が目玉として推進された。この郵政民営化では官がやっていることの非効率性、不採算性が強調され、官業が民業を圧迫していると非難しながら、その民営化の必要性が主張された。
ここで官業が民業を圧迫していると非難する理由の最たるものは、郵便貯金と簡易保険である。銀行が危ない、保険会社が頼りにならないという状況のなかで、一般庶民が最も安心して預けられる所は郵便局である。この庶民が預けた零細な金が積もりに積もって、2004年3月末には345兆円(郵便貯金227兆円、簡易保険118兆円)に達した。これは日本の個人金融資産の約4分の1に当たる。これが銀行などにとっては憎くてしようがない。だから「郵便貯金は廃止せよ」というのが銀行協会の持論であった。こうした銀行や保険会社や外資の要求が、小泉首相の民営化論の背後にはある。民営化によって、銀行や保険会社や外資は、その宝の山に参入することができるのだ。
その民営化の割を食うのは一般庶民と労働者である。庶民が安心して預けられる所がなくなるし、僻地などは郵便局がなくなって、非常に不便なことになる。また郵政労働者にとっては、それ以前からすすめられているリストラ合理化が民営化とともにいちだんと苛酷なものになることは、国鉄民営化の先例を見るまでもなく明らかである。
こう見てくると、小泉経済構造改革は、独占資本の要求に最もかなうように経済構造を改革しようとするものであるといえる。だから、経団連を中心とする財界は献金を積極化して、小泉改革を全面的に支持している。小泉首相は「自民党をぶっ壊す」といったが、壊すのではなく、独占資本主流の志向する方向とそぐわなくなった部分をそぎ落として、現在の独占資本主流の意向に最も適したあり方に、自民党を仕立て直そうとしているのである。
■ 大衆へのしわ寄せ
小泉改革の第三の柱は財政改革である。その背景にあるのは財政難の深化である。バブルがはじけた90年代の初めから、政府は不況打開のため財政面からのテコ入れをいちだんと強めた。その中心をなしたのは公共事業であり、公共事業を中心とする総合経済対策が、その後10年間に12回打たれ、あわせて約135兆円の金が撒布された。そしてそれをまかなうために国債が増発され、国債残高がじりじりと増えた。国だけではない。地方自治体も政府の不況打開策の片棒を担わされて、公共事業を増やし、借金を重ねた。こうして国と地方を合わせた長期債務残高が、2005年度の終わりには774兆円に膨らんだ。国内総生産の実に1.5倍である。政府の野放図な財政バラまき策が、こうした借金の増大、財政難の深刻化を生んだのだ。
だが、こうした自らの責任は棚上げにしたまま、財政難の深化だけを強調して、それを打開するための財政改革の必要性を訴えた。そしてその打開策としてまずすすめたのが経費削減であった。この経費削減は各方面にわたったが、なかでも力が入れられたのは、社会保障費の節減と地方自治体へのしわ寄せであった。
社会保障については、高福祉・高負担は社会の活力をそぐとして、「活力ある福祉社会の建設」をうたい文句とし、個人の自助努力を強調して、受益者負担をふやし、国の福祉費負担の軽減をはかった。日本の国内総生産に占める社会保障費の割合は、国際的に見てまだ低いのに、財政難の打開を口実として、さらなるその抑制がはかられた。そして医療、年金などの社会保障を改悪し、受益者負担をそのたびに増やしていった。こうして国民の健康と老後を保障する安全のネットワークは細る一方であり、国民生活はいよいよ不安定になっている。これから定年を迎える「団塊の世代」の老後はまさに「断崖の世代」である。
経費削減の第二のターゲットは地方自治体である。政府は自らの財政再建を優先させて、地方自治体へのしわ寄せを強めた。地方自治体の反発に、政府は一応「三位一体の改革」((1)国の地方への補助金削減、(2)地方交付税の見直し、(3)税源の地方自治体への移譲)なるものを決めた。だが、三年たったその実情は、国の削る補助金や地方交付税の額にたいして、移譲される税源はかなり少なく、地方自治体の財政難が依然としてつづいている。
また、こうした財政難の地方自治体にたいして、政府はアメとムチの政策をもって、市町村の合併を迫り、「平成の大合併」が進展した。そして、そのねらいもまた経費削減にあった。しかも、この市町村合併のさらに先には、財界の要望する「道州制」の導入がもくろまれている。こうした「地方分権」とは名ばかりで地方財政のしめつけをテコとして、さらなる中央集権体制の構築をめざしているというのが小泉改革の実態である。
さらに小泉改革の経費削減のターゲットとして、今日強められつつあるのが公務員の総人件費の削減である。日本の人口千人当たりの公務員数は、先進国の中ではきわめて少ないのに、それをさらに減らし、国家公務員数を今後5年間に5%、地方公務員を4.6%純減にするという。また賃金についても、賃下げ、地域給の導入、能力主義化といった新たな攻撃がかけられてきている。その攻撃の援護射撃として、マスコミを通じた公務員バッシングも強められている。こうした公務員攻撃はたんに経費削減ということだけではない。なお残る抵抗勢力としての公務員の組合を骨抜きにしようというねらいをももつものである。
しかし、こうした経費削減で現在の財政難を打開できるという見通しはない。そこで、強められだしたのが増税である。その第一着手が所得税の増税であり、まず手はじめとして各種控除の廃止ないし減額が進行しつつある。たとえば、特別扶養控除、老齢者控除、年金控除、基礎控除、扶養控除などの廃止ないし減額がつぎつぎにおこなわれつつある。これらの控除が廃止ないし減額されると、それだけ所得税が高くなる。またこれまで所得税がかかっていなかった人にもかかるようになる。さらに所得税と個人住民税に、これまで「景気対策の恒久的減税」として実施されていた定率減税が、半減され、さらに全廃されようとしている。これも即、増税である。
このように一般庶民が増税されている他方で優遇されているのが高額所得者と法人である。高額所得者の最高税率は、かつての70%から今や37%と大幅に下がっている。法人税の基本税率もかつての43.3%から近年は30%にまで下げられた。小泉改革のもとで貧富の差が拡大している現状を考えるのならば、貧困者の税は軽く、富裕層の税こそ高くなるべきなのに、事態はまったく逆の方向をたどっているのだ。
さらに次なる増税の本命として控えているのが消費税である。消費税を1%上げると約2兆2000億円の増収になる。だから、この税率を2007年度から、大幅に上げようという計画が着々と進行している。消費税はいうまでもなく「逆進性」をもつ、貧困層泣かせの大衆課税である。この大衆大増税時代がいよいよ来ようとしている。税金は本来、不平等な所得を再分配するという機能をもつものである。だが、その機能を喪失し、貧しい者からいよいよ搾り取る階級的性格をあらわにしているというのが、現在の税制改革の方向である。
■
こう見てくると、小泉改革が、労働者や一般大衆のためのものではないことは明確である。財界主導の新自由主義的構造改革であり、労働者をはじめ中小企業、農民その他広範な国民の生活を犠牲にしながら、矛盾を深めた資本主義の現状を打開し、時代適合的な独占支配体制の再構築をはかるものといわなければならない。この独占資本本位の小泉改革に相対して、広範な国民の生活を守る反独占のたたかいをどう構築していくかが、われわれに課されている重要な課題である。
|
|
本サイトに掲載されている記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright (c) 2024 Socialist Association All rights reserved.
|
|